ヨーロッパのリサイクル事情 スペイン編 Vol.4
〜環境配慮の落とし穴 – 本当にサステナブルな選択とは?〜
今回も本コラムをお読み頂き誠にありがとうございます。
日本シーム 岩渕でございます。
前回のコラムでは、スペインで進む消費者主導型の環境配慮型経済のお話をしました。そして、この消費者主導型のパラダイムシフトにはひとつ大きな落とし穴がある、という結びで今回のコラムへ繋ぎました。今回は、その落とし穴について、詳しく述べていきます。

環境配慮の意外な落とし穴――プラから紙への代替の光と影
その落とし穴とは「本質的に何が環境に良いのか」という点を見誤ると、その経済は誤った方向に進んでいってしまうという点です。つまり、一見すると環境に配慮ある製品・施策に見えても実は効果がないこと、あるいは実は環境に悪いことが続けられれば、地球環境は改善しない、もしくは悪化していく可能性を孕んでいるということです
ひとつ例を挙げてみましょう。日本と同様、欧州でも脱プラの動きが加速し、包装材等の分野で紙への代替が進んでいます。飲料パックはもとより、詰め替え用のシャンプー等も紙の包装が目立つようになりました。話は外れますが、この詰め替え用のシャンプーは非常に優れものです。シャンプはー粉の状態で紙包装に包まれており、ボトルに入れて水と混ぜることで液体シャンプーへと変身するのです。欧州旅行の際はお土産にどうぞ。さて、話を本筋に戻します。このプラから紙への代替は、プラの使用量削減策として確かに効果があると思います。
ただしそれは、単一の紙原料のみに代替されている場合に限る、というのが私の個人的見解です。特に食品包装等の分野では、バリア性等を担保するため紙とプラの積層材が氾濫しています。こういった積層材では、確かにひとつのパッケージあたりに使用するプラの量は減っているかもしれませんが、紙の混入はプラスチック側のリサイクルにおいては問題です。
再生製品の品質低下や、マテリアルリサイクルの対象とはならず燃料としての再利用といった結果を招いてしまうからです。これはあくまでも一例ですが、良かれと思ってプラを紙へ代替した結果として、リサイクルできないプラを増やしてしまうという流れを垣間見て頂けましたでしょうか。

「環境に良さそう」の落とし穴とリサイクルの本質
こうしたパラドクスは「紙が使われたパッケージは環境に良さそう」という消費者側の視点、需要に端を発して広がっていきます。そして結果としてリサイクルできないプラが増え続けてしまう、このような流れこそが落とし穴の正体です。
消費者が環境問題に関心があるからこそ、環境に悪影響を及ぼしてしまうというのは非常に残念なことですが、この逆理を未然に防ぐことは非常に難しいことであるように思います。なぜならば、マテリアルリサイクルの工程や、環境機械にできること、できないこと等、非常に専門的な知識無くしては「本質的に何が環境に良いのか」を判断することは困難だからです。
前回も登場したANARPLAのプレゼンテーションでは「プラスチックは悪ではない。プラスチックがリサイクルされないことが悪である」という主張が強調されました。すなわち、全てのプラスチックが正しくリサイクルされていれば、プラスチックは環境に良いマテリアルであり得るということです。そして「正しくリサイクルされる」とはどういうことなのか、あるいは消費者や生産者が製品の持続可能性をどのように評価したら良いのか、そうしたテーマを発信し理解を深めていくことも、我々のような静脈産業に関わる企業の責務なのかもしれません。


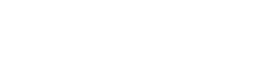
 洗浄粉砕機
洗浄粉砕機 破砕機
破砕機 高精度洗浄設備
高精度洗浄設備 粉砕機
粉砕機 切断機
切断機 水処理設備
水処理設備 微粉・細粒機
微粉・細粒機 乾燥機
乾燥機 プラ洗ユニット
プラ洗ユニット 洗浄脱水機
洗浄脱水機 減容・造粒機
減容・造粒機 選別機
選別機 混合機
混合機 分離機
分離機 搬送装置
搬送装置





























