ヨーロッパのリサイクル事情 番外編
〜リサイクルを支える隠れた工夫 – 動静脈連携の真価〜
今回も本コラムをお読み頂き誠にありがとうございます。
日本シーム 岩渕でございます。
前回までのコラムでは、全4回に渡ってスペインのリサイクル事情についてお話をしてきました。そして前回は、消費者主導型の環境配慮経済に潜む落とし穴というテーマでスペイン編の締めくくりとさせて頂きました。今回は、その続きでもあり、番外編でもあり、欧州における動脈産業と静脈産業の関わりについてお話をしたいと思います。

作る側と再生する側の素敵な協力関係
スペイン編Vol.3のコラムにおいて「有名な濃いブルーボトルのミネラルウォーターが、リサイクルしやすくするためにボトルのブルーの色を薄くした」という事例をご紹介しました。これは消費者側の環境配慮指向に応える形で生産者の動向が変わった一例としてご紹介したエピソードですが、もう一つ大事な事実が隠れています。
それは「静脈産業側の都合に合わせ、生産者の動向が変わった」という点です。欧州において、こうした例は枚挙に遑がありません。例えば、ブランドカラーとしてボトルに黒色を採用していた洗剤ブランドが、ボトルの色を「光学選別機に読み取れる黒色」に変えたり、製品材質の密度を変えた結果として比重選別が上手くできず、元の密度に戻したり・・・等、生産者が静脈産業側の都合、さらに言えばリサイクルプラントや環境機械の性能に適合するように製品を開発・改良するという事例を多く見つけることができました。
欧州視察を通じて「欧州のリサイクルは先進的だ」という漠然とした印象を最も強く意識したのは、まさにこうした動脈産業と静脈産業の関わりを感じた時に他なりません。

取れないキャップの秘密 – ドイツに学ぶペットボトルリサイクルの知恵
せっかくですので、もう少し具体例を挙げてみましょう。こういったケースの最たるものがドイツのペットボトルのリサイクルだと思っています。日本においても、ペットボトルはリサイクルの優等生と表現されるくらい再生率の高い製品であり、その再生フローには分別という形で私たち市民も大きく関わっています。一方、ドイツでは少し様相が異なります。
まず、ドイツでは基本的には日本のような部位ごとの分別は行われていません。日本ではラベルを剥がし、キャップを取り、ボトル内部を濯いで潰して・・・という捨て方が浸透しましたが、ドイツは各所に設置されたデポジットマシンによる回収が一般的です(詳しくはドイツ編Vol.2参照)。そして、デポジットマシンにはキャップもラベルも付いたままで投入します。
それもそのはず、ドイツ国内で生産されるペットボトルはキャップがボトルから外れない構造を採用しており、ラベルにはデポジットマシンが読み取るためのバーコードが印字されています(ちなみに、現在ドイツではキャップが外れるタイプのペットボトルは生産できません)。一見すると日本式の分別回収の方が進んでいるようにも感じますが、ドイツはなぜこのような仕組みを採用しているのでしょうか。
それは、一口に言えば「プラスチックを根こそぎ集めるため」といったところです。もちろん、文化的に分別回収が浸透しにくいという理由もありますが、デポジット式を採用することでキャップやラベルも取りこぼさずに回収することができるというわけです。
私が感動したのはその先です。この開封しても首の皮一枚繋がるように設計されたキャップ、この構造が最も威力を発揮するのはリサイクルプラントに投入された時です。ペットボトルに限らず、欧州の多くのリサイクルプラントにはその冒頭に異物やオーガニックと呼ばれる食品系残渣を除去するためのドラム型スクリーンが待ち構えています。このスクリーンの穴径は大体φ40〜50mm程度が一般的であり、キャップがボトルから外れてしまった場合、このスクリーンの目穴を抜けて異物や残渣に紛れてしまうのです!このスクリーンを無事に通過させるため、ドイツのペットボトルはキャップが外れないのです!

共創がもたらすリサイクルの未来 – 日本の進むべき道
あれ?もしかしてこんなに盛り上がっているのは私だけでしょうか。この話を始めて聞いた時、環境機械メーカーの社員として、機械の都合に生産者や法律が合わせてくれるなんて夢のような話だと感動したことを覚えています。さて、少し冷静になって続きを書きます。日本のリサイクルに足りていないところ、言い換えれば日本のリサイクル率をぐっと引き上げるためのキーは、まさにこのような動静脈の連携なのではないでしょうか。
機械メーカーとしては言いにくいことではありますが、機械の性能には限界があります。だからこそ、我々のような静脈産業に関わる企業と生産者が意見を交わし、一丸となって取り組んで行けば、日本のリサイクルにはより良い未来があると信じてやみません。

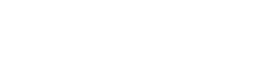
 洗浄粉砕機
洗浄粉砕機 破砕機
破砕機 高精度洗浄設備
高精度洗浄設備 粉砕機
粉砕機 切断機
切断機 水処理設備
水処理設備 微粉・細粒機
微粉・細粒機 乾燥機
乾燥機 プラ洗ユニット
プラ洗ユニット 洗浄脱水機
洗浄脱水機 減容・造粒機
減容・造粒機 選別機
選別機 混合機
混合機 分離機
分離機 搬送装置
搬送装置





























